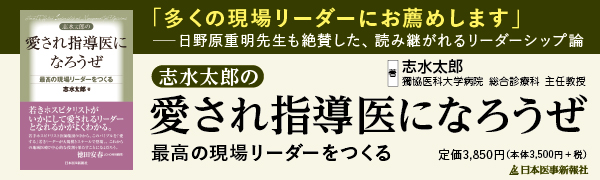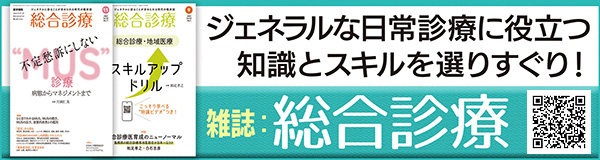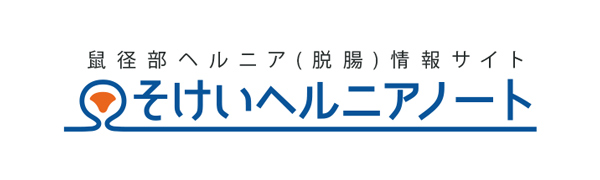初回の髄液検査で細胞数増多がなく,診断遅延を来たした単純ヘルペス脊髄炎による神経原性ショックの一例
【背景】単純ヘルペスウイルスによる脊髄炎は稀な中枢神経感染症の1つである.上行性の脊髄障害を特徴とする予後不良の疾患であり,早期診断と治療介入が必要である.【症例】59歳,男性【主訴】意識障害【病歴】アルコール依存症で近医精神科にてジスルフィラムを処方されていた.来院当日,自宅で倒れている所を発見され救急搬送された.【所見】GCS E1V1M1,体温 35.8℃,血圧 41/29mmHg,脈拍 83bpm,SpO2 100%(O2 10L投与下).体表面に外傷なし.血液検査所見:白血球数 12300/μL,Hb 11.2g/dL,血小板数 22.5万/μL,BUN 18.2mg/dL,Cre 1.7mg/dL,Na 139mEq/L,K 2.9mEq/L,Cl 101mEq/L,血糖 147mg/dL,アンモニア 17μg/dL未満,アルコール 220mg/dL,ビタミンB1 106.5ng/dL,CRP 0.05mg/dL.頭部CT:頭蓋内出血や占拠性病変を認めず.【経過】ジスルフィラムアルコール反応による低血圧の診断で入院とした.第2病日に昇圧薬は終了でき会話も可能となった.意識改善後の診察で両下肢の脱力と腱反射の消失があり,胸腰椎MRI(STIR)で髄内高信号領域を認めた.髄液検査で細胞数2/μL,髄液HSV PCR 2×102コピー未満(陰性)であり,脊髄炎ではなく脊髄梗塞と診断した.第13病日に発熱,意識障害,項部硬直が出現し髄液検査を再検したところ,細胞数246/μL(単核球221/μL),髄液HSV PCR 8×106コピー(陽性)であった.髄液検査後に撮像したMRI(STIR)では,髄内高信号領域の上行性拡大を認め単純ヘルペス脊髄炎と診断した.【考察】後方視的には単純ヘルペス脊髄炎による脊髄障害,神経原性ショックで一元的に説明可能であった.しかし,来院時に意識障害があり薬剤性低血圧で説明可能と考えられたことから,開梱の失敗・診断の早期閉鎖が生じた.また,脊髄病変確認後の髄液検査で細胞数増多を認めなかった際にも診断の早期閉鎖が生じ,診断遅延につながったと考えられた.【結語】神経原性ショックを覚知できず,その後の髄液検査で細胞数増多がなかったため診断遅延となった単純ヘルペス脊髄炎,神経原性ショックの一例を経験した.