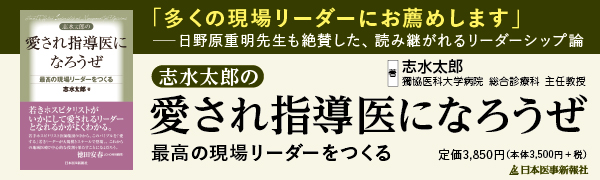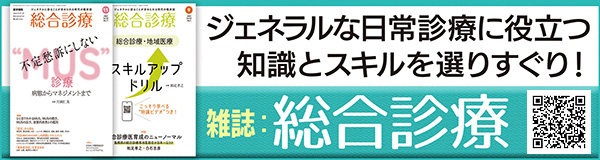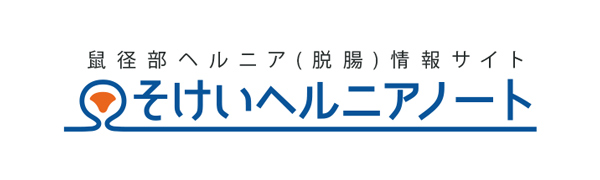東洋医学の臨床推論―診断学を駆使した弁証論治を目指して―
【背景・目的】近年,国際疾病分類(ICD-11)に伝統的な東洋医学の章が追加され,今や東洋医学は世界的に再評価されつつある.日本においても東洋医学としての漢方・鍼灸分野は徐々に興味関心を持つ医療者が増えている.一方で,東洋医学的な診断過程が難解だと考え障壁を感じている初学者にもよく出会う.東洋医学の思考過程を未修学者や初学者にもわかりやすく説明することを試みる.
【方法】実際の東洋医学の症例の診断過程を提示し,現代の診断学と同様の思考プロセスが用いられている箇所を抽出し検討する.
【結果】東洋医学的診療においても,System1,System2に加えPivot and cluster戦略に類似した思考過程が用いられていた.
【考察】日本漢方での証(診断名)の決定は,使用する漢方の使用目標が目の前にいる患者さんに合致するかどうかを見極める思考プロセスが主となり,言わばクリニカルパールを駆使したSnap診断である“System1”の要素が大きい.「弁証」とは中医学での病態の分析と診断の過程を指し,極めて分析的でありいわゆる“System2”の思考プロセスを主体として用いる.さらに,志水らが提唱したPivot and cluster戦略を東洋医学に応用することは,中医弁証や日本漢方での証の決定において,東洋医学的に類似した臨床像の鑑別病態の想起や使用目標の近似した漢方薬の処方の決定に大いに役立つと考えられる.
【結語】東洋医学的診断のおおまかな過程は,System1,System2,Pivot and cluster戦略を用いて説明することが出来そうである.今後も今回のような発表のフィードバックを受け、東洋医学的診断過程をわかりやすく伝えることに尽力していく.