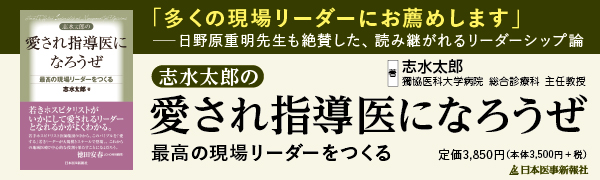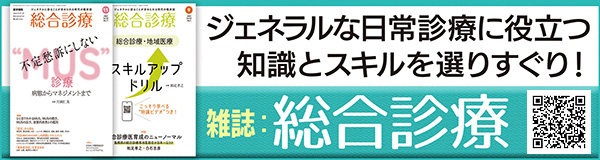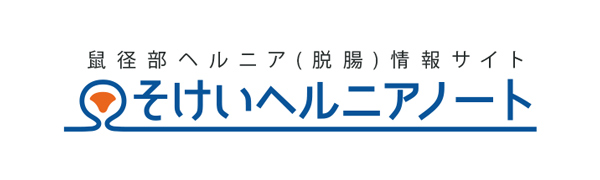診断過程の意思決定に活かす経営学の理論と実践
1982年9月29日、米国の鎮痛剤市場で最大のシェアを誇っていたタイレノールにシアン化合物が混入し、米国イリノイ州で12歳の少女が死亡。以後計5瓶の同薬によって計7名の死者が発生し、全米を震撼させた・・・。事件の数時間後にこの一報を聞いたメーカーの最高経営責任者バークは、まったなしの意思決定を迫られました。
総合診療医の皆様は日常診療において数多くの意思決定をされていると思います。どの検査を実施するか、誰にコンサルトするか、どのタイミングで治療に踏み切るか‥。ビジネス分野でも同様に、経営者はこのような緊急のものから、長期戦略の決定まで、常に意思決定を積み重ねています。
意思決定の科学は、様々な科学領域にまたがるものですが、ノーベル賞経営学者サイモンが「経営することと意思決定することは同義である」と言ったとおり、経営学においても主要な一領域であり、学術面および実務面から、これまでに多くの知見が蓄積されてきました。本講演では、「アナロジー」という手法を用いて、これらの経営意思決定における知見を診断学の各要素に対応させ、総合診療への経営学の実装を試みます。
本講演はまず、診断過程における意思決定に関する医学的知見を座長から共有します。続いて、経営における意思決定の基礎理論および経営実務での適用について紹介します。具体的な項目として、経営における意思決定の位置づけ、意思決定の基本要素、意思決定プロセス、組織における意思決定、不確実性下の意思決定、リアルオプション(決定の柔軟性)、およびエフェクチュエーション(起業家に見る高不確実性下の意思決定原理)を取り上げます。
各々のパートごとに、診断過程とのアナロジーを考える時間を設ける予定です。社会科学領域で蓄積された意思決定の知見を、病院総合診療において適用できる機会を、皆様と共に探っていきたいと思っています。