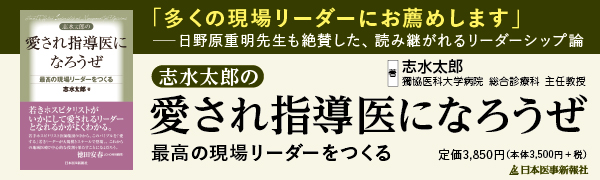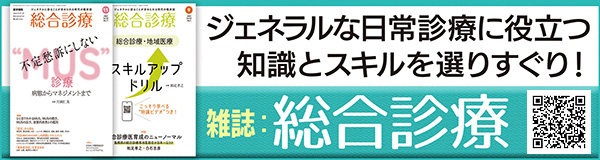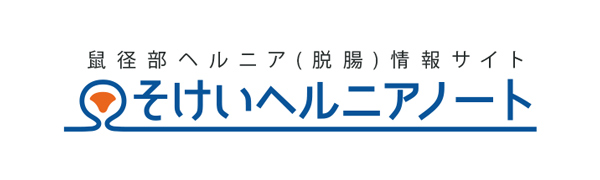診断プロセスを通じて行う病の意味の共創
不定愁訴については様々な説明があるが、それらに共通するのは「適切な検査を経ても明確な診断がつかず、愁訴が継続し、ときにその内容が変化するもの」といった特徴である。海外ではMedically Unexplained Symptoms(MUS)、あるいは、より患者中心の表現としてPersistent Physical/Somatic Symptoms と呼称される。プライマリ・ケア現場における疫学には様々な報告があるが、実に15-45%程度の患者がこのMUSに該当すると言われている。
Diagnostic excellenceという観点からは、患者の中に隠れている診断を適切に見つけ出すことについて、医師のたゆまぬ研鑽が重要であることは言うまでもない。一方で、MUSの中には現在の科学の限界として診断名を付すことができないものも含まれるため、いかに診断学に精通した医師であろうとも、診断名がつかない病態に対峙することから逃れることはできない。この講演ではこうしたことを念頭におきながら、MUSについて知っておくべきポイント、診断という行為の利点と注意点、wellbeingという視点を踏まえたMUS診療のゴールについて話していく。演者はMUSの診断プロセスを、医師が患者の中に隠された問題を探り当てるという客観的な作業(mining model)というよりも、知の互恵性(epistemic reciprocity)に価値をおきながらwellbeingのエキスパートである患者と病の意味を共創していく作業(travelling/explanatory model)と捉える視点を提案・紹介する。