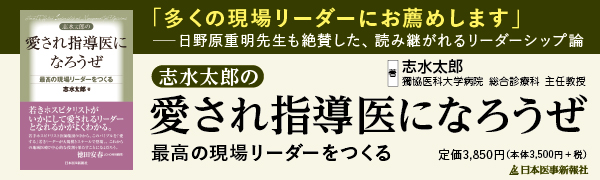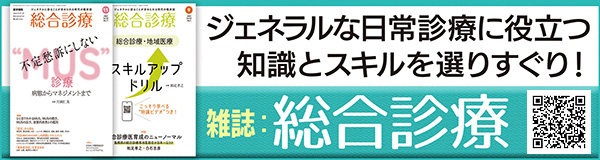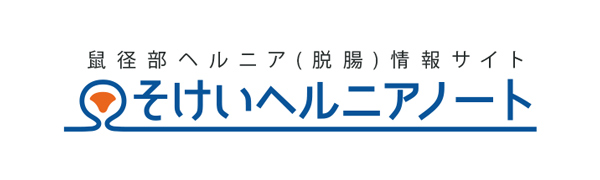医療診断における認知バイアスを考える
おおよそ半世紀にわたって展開してきた、認知科学を中心とした心の科学は、心理学、神経科学、情報科学、社会学、人類学等との共同により、認知のプロセス、メカニズムについて多くの知見を提供してきた。この知見の中の一つに、認知バイアスがある。認知バイアスは、認知の歪み、偏りを指し、知覚から始まり、記憶、思考、判断、共同に至る認知のプロセスのほぼ全ての段階に存在している。これらのバイアスは、簡単な教示やアドバイスでは簡単に克服できるものではないことも明らかにされている。だから、十分な教育を受けた大人であっても、規範的な理論から逸脱した非合理的、非論理的な認知を行ってしまう。本講演では、医療診断と関係が深いと思われる4つの認知バイアスを取り上げ、実験例を通して認知の歪みを解説する。1つ目は注意である。私たちの注意システムは非常に限定されており、状況の中の一部にしか働かないことがままある。2つ目は判断である。私たちはある仮説を持つと、その仮説を肯定するような事象に注意を向けがちになり、反証例を無視してしまう傾向がある。3つ目は言語によるバイアスである。私たちは言語的コミュニケーションを通じて情報を共有するが、言語が関わることで覆い隠されてしまう情報も存在する。最後は共同である。前述の3つのバイアスは診療場面で重大な判断ミスを引き起こす危険性があるが、他のメンバーとの共同によって克服されると考えられるかもしれない。しかし共同は同調などの別のバイアスを生み出すことも多い。これらのバイアスは直感的、無意識的に働くため、その克服は容易ではないが、克服のヒントとなる可能性のある実験例を紹介する。