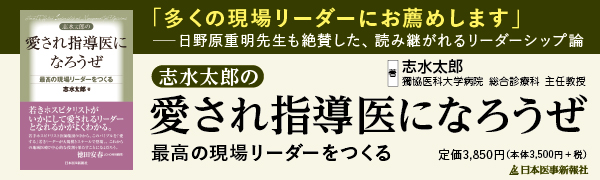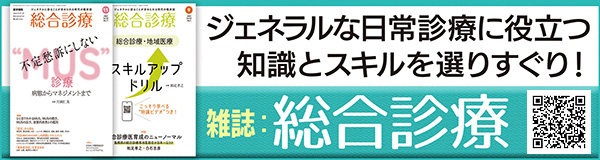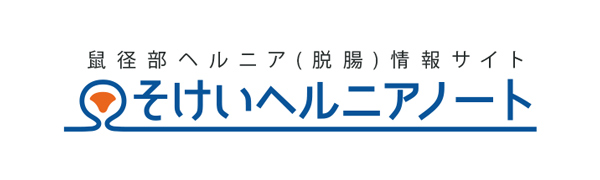典型的な症状を持たない低ホスファターゼ症を早期診断する意義について
低ホスファターゼ症(HPP)は、組織非特異的アルカリホスファターゼ遺伝子の変異により、呼吸困難、痙攣発作、成長障害、硬組織の石灰化不全、乳歯の早期脱落、を主徴とする先天性疾患である。HPPの診断は、家族歴、胎児エコーでの長管骨の低形成や彎曲、もしくは乳歯の早期脱落を認めて、初めてHPPが疑われ、種々の検査を経て確定診断に至る。そのため、4歳以上の小児型HPP、成人型HPPや歯限局型HPPは、HPPであるにも関わらず、HPPとの診断がつかずに骨粗鬆症、関節リウマチや歯周病と診断されることがある。
その結果、HPPには適さない投薬や処置が行われ、結果として症状の悪化を来す症例もある。例えば、骨粗鬆症の治療薬として幅広く使用されているビスホスホネート(BP)製剤の投薬は、症状の改善を期待できないばかりか、非定型大腿骨骨折の発生につながるとの報告もあり、日本小児内分泌学会のHPP診療ガイドラインにもHPP患者に対し、BP製剤の投与を避けるべきという記述がある。しかしながら、HPPと診断がつかずにこのような事態が避けられるかどうか疑問が残る。
そこで本シンポジウムの発表では、典型的な症状を持たないHPPのモデルマウスであるAkp2+/-マウスを対象に、BP製剤の投与が大腿骨に与える影響をご紹介させて頂き、早期診断する意義について考え、今後の課題について共有させて頂きたい。