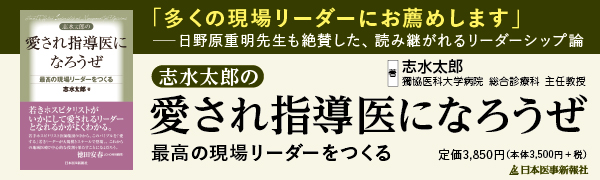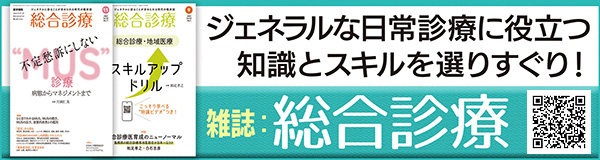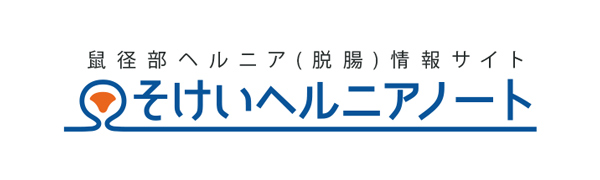東洋医学、もう一つのとても役立つ診断学
臨床医として、こんなことをできれば、実践してみたいと思いませんか。
それは、「1つの症例で、診断戦略を複数持ち、様々な治療戦略を持つこと」です。
本セッションでは、その足がかりとなる東洋医学的診断戦略・治療について、解説を加えます。
西洋医学の世界では、診察において「問診8割、身体所見1割、検査1割ほどで診断に貢献する」と言われます。
では、血液検査や画像検査がなかった時代、つまりは東洋医学メインの時代はどうだったのでしょうか。
検査の1割はどちらに振り分けられるのでしょうか。
より細やかに病歴を確認していたのか。
それとも舌診や脈診といった東洋医学独自の身体所見が診断に与える影響力が強かったのでしょうか。
いずれにせよ、検査が存在しないため、病歴や身体所見からより細かに情報を導き出して、診断や治療に結びつけていたと推定されます。
今回は、東洋医学を実践している先生方をお招きし、その頭の中を垣間見たいと思っています。
実は、System1・Sytem2やPivot and Cluster Strategyといった普段馴染みのある思考過程も多く存在します。
また、治療戦略として、漢方薬処方に限らず鍼(はり)や灸(きゅう)という戦略も存在し、当日披露したいと考えています。
ぜひ、東洋医学を学んで、1つの症例で診断・治療戦略を複数持つ臨床医を目指しましょう。