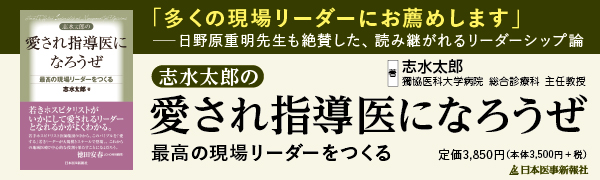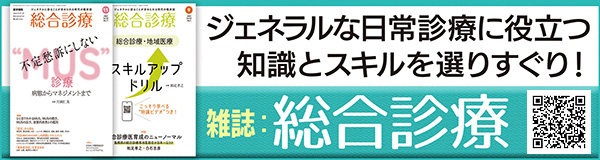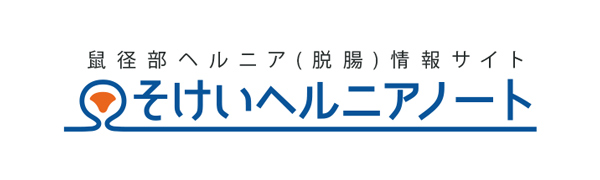[O-025] NDBオープンデータを活用した大学病院総合診療科における慢性腎臓病と腎性貧血の有病率等の把握
【背景】慢性腎臓病(CKD)は生活習慣病等に起因し、無症状で進行し、心血管病や末期腎臓病の原因となる。治療による進行抑制・合併症回避が可能であり、早期診断が重要である。CKDの合併症である腎性貧血については内服治療薬の登場もあり、早期診断の重要性は増している。しかし、大学病院総合診療科を含めた臨床現場でのCKDや腎性貧血の有病率の把握は不十分である。【方法】2018-2020年に当科を受診した外来患者の診療データと、当院が含まれる医療圏である東京都区南部のNDBオープンデータを用いて観察研究を行った。【結果】1)院内データでのCKDとHb値の検討当院受診患者8,678名を対象にして、Hb11g/dL未満を貧血と定義した際の(1)eGFRに基づくCKDステージ、(2)65歳以上、(3)性別を説明変数とした貧血の規定因子に関するロジスティック回帰では、CKDステージ、65歳以上、女性が独立した因子として抽出され、CKDステージのOdds比は1.26(95%CI:1.10-1.42)だった。2)区南部健診データとの貧血及びCKDの有病率の比較当院を受診した40-74歳の患者4,365名と15,700余名の特定健診受診者について、WHO基準に基づく貧血の有病率は健診データでは男性0.6%、女性5.7%に対して当院受診者では男性9.0%、女性16.7%とともに高く、CKD stage3以上の患者の有病率は健診データでは男性9.5%、女性44.8%に対して当院受診者では男性24.5%、女性24.9%と性別を問わず貧血患者,CKD患者ともに割合が多かった。【考察】1)腎性貧血に対する治療を目的とせずに様々な患者が受診する大学病院総合診療科においてもCKDは貧血の規定因子であり、未治療の腎性貧血患者が多く潜在している可能性が示された。2)CKDの治療を目的とせずに様々な患者が受診する大学病院総合診療科においても、CKDや貧血の患者の有病率は検診対象者よりも非常に高く、従って治療介入を要するにもかかわらず放置されている腎性貧血患者を拾い上げ、治療の実態を調査するうえで適切な受診環境(患者群)である可能性が示された。