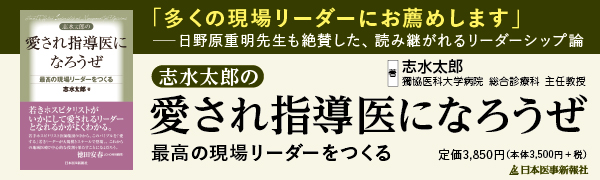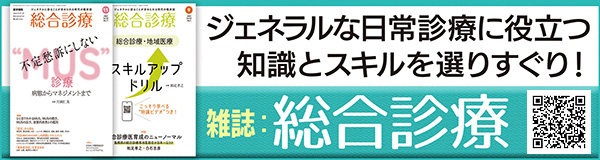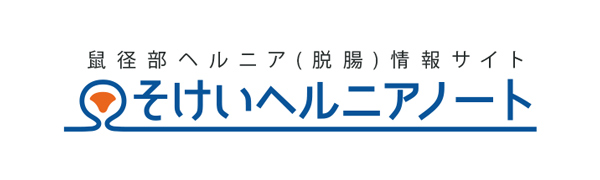[O-033] 診断エラー学講義の医学生への効果:単施設横断研究
【目的】診断エラーは診断プロセスの誤りによる診断の遅延・誤診・見逃しの総称である。診断エラーを含む医療過誤は米国での死因の第3位とされ、日本でも医療裁判で賠償命令が出た事例の47.5%が診断エラーによるものとされている。このため、医療現場に出る前の医学生のうちから、診断エラーの概念を教育することは重要である。医学生に対する診断エラーの講義の効果を調査するため、本研究を実施した。【方法】2022年10月の診断エラーの講義(60分)に参加した佐賀大学医学部4年生を対象とした。講義では、診断エラーの定義、背景、要因(認知要因、システム要因、患者要因)、学習意義、認知バイアス、システムエラー、fishbone diagramを解説し、症例問題を通してエラーの要因を考察した。翌日の試験では症例問題を出題し、診断エラーに関与した認知バイアスとシステムエラーを記述させ、回答数を集計した。【結果】4年生は合計102名で、講義欠席者15名と研究参加に同意しなかった4名を除く83名を対象とした。男性は40名(48%)であった。試験で回答された認知バイアスは全7種類で、一人当たりの中央値は2(1-3)種類であった。診断の早期閉鎖が73%で最も多く、次いで確証バイアス(53%)が多かった。システムエラーは全5種類で中央値は4(3-4)種類であった。最も多かったのは「他の医療者とのコミュニケーション(99%)」で、次いで「担当医の長時間労働による疲労(95%)」であった。認知バイアスとシステムエラーの一人当たりの合計回答数は5(5-7)種類であった。【考察】診断エラー症例には5-6種類の認知バイアスとシステムエラーが同時に関与しているとされる。本研究において、医学生は、60分の講義の翌日の試験で5種類の認知バイアスとシステムエラーを回答していた。このことから、臨床現場を未経験の医学生でも、講義により診断エラーの要因を適切に振り返ることが可能になることが示唆される。【結論】診断エラーの講義は、臨床実習前の医学生による診断エラー症例の適切な振り返りを可能にする可能性がある。