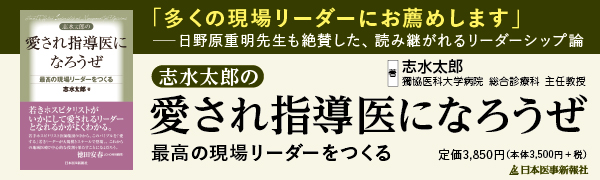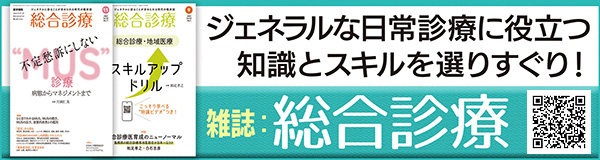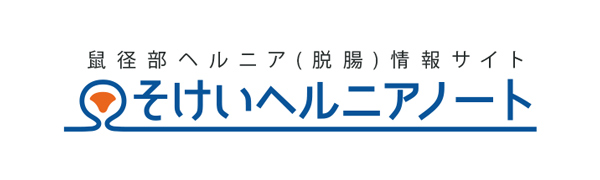[O-035] AIによる胸部大動脈所見の読影 〜実臨床における胸部単純CTのAI全例読影の有用性〜
【緒言】
大動脈疾患の多くは無症状で進行し、しばしば他疾患精査目的の画像検査で偶然指摘され診断に至る。一方で、画像検査を施行した医師は、自身が想定した疾患に関連する領域の読影精度は高いが、偶然撮影された所見の検出率は低く、疾患見落としに関連することも知られている。近年、AI(人工知能)による読影サービスが始まっており、医療従事者の労務的・精神的負担軽減と、専門医による読影がなされない画像において偶然撮影された病変の見落とし回避に有用ではないかと期待されている。
【方法
】2022年2月1日から28日までを本研究の対象期間とした。当該期間には放射線科医によるCTの全例読影はなされておらず、特に主治医が必要と判断した例のみ放射線科読影依頼がなされる体制であった。同期間に鎌ケ谷総合病院救急外来にて施行された胸部単純CTの全例読影をAIにより行い、全読影結果を本研究の検討対象とした。AI読影に用いたアプリケーションはAI-Rad Companion CT (Siemens Healthineers, Erlangen, Germany)であった。AI読影の結果は検査翌日に電子カルテ上に反映された。後日、本研究のために、対象となった単純CT画像の大動脈所見を心臓血管外科専門医が読影し(以下、読影医)、AI読影の結果と比較した。距離として10%以上の差が生じたものを読影に差が生じた例と定義した。
【結果】90件の胸部単純CTが検討対象となった。年齢 中央値82(範囲20-99)歳、男性:女性=45:45人。AIと読影医の読影結果を比較した結果は以下の通りであった。大動脈と判別された領域が異なった例=34(38%)、大動脈径の計測結果が異なった例=17(19%)、AIが読影医よりも大動脈径を過小評価していた例=0、動脈瘤が実際に認められた例=0であった。読影に差が生じた部位のうちでは大動脈基部が28例(82%)で最多であった。51例(56%)で放射線科読影の依頼なく、主治医による救急外来での読影のみで画像の評価が終了していた。
【結論】3割にAIと読影医の大動脈径計測値に差が認められたが、AIが動脈径を過小評価した例はなかった。大動脈径拡大に対してAI読影は感度が高く特異度が低いと考えられた。この特性を考慮すると、AI読影を活用することで、主治医から放射線科へ読影依頼がなされないCT検査において、偶然撮影された大動脈疾患があった場合に主治医に注意喚起することで見落としを予防できる可能性がある。一方で、現時点では陰性的中率は低いため「診断」には主治医に加えて放射線科または専門診療科医師による読影は必須と考えられた。