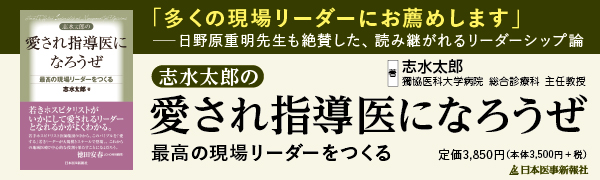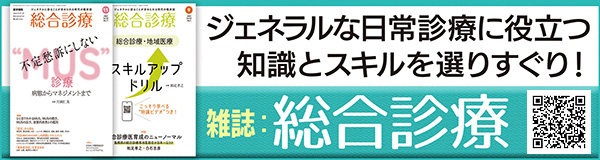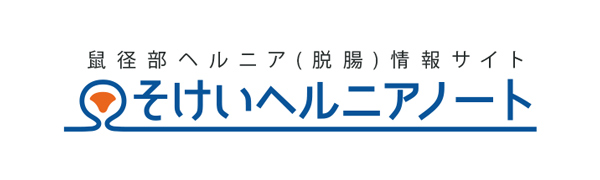[P-073] 30年以上の使用歴がある抗てんかん薬により遷延性の発熱を来した1例
【背景】重症心身障害を有する者の不明熱精査は十分な問診ができず、しばしば難渋する。今回、網羅的な不明熱精査を行い、抗てんかん薬の変更により改善を得た1例を経験した。【症例】37歳女性【主訴】発熱【既往歴】乳児期発症のてんかん発作による重症心身障害があった。てんかん発作は難治性であり、強直間代発作を繰り返し、精神運動発達遅滞を有した。【現病歴】34歳時より当院で長期入院療養中であった。誘因なく発熱が生じ、37.5℃から40℃の間で経過した。抗菌薬に反応せずに2週が経過し、小児科とリウマチ科で精査した。【身体所見】血圧と酸素飽和度は保たれ、脈拍は体温に応じ上昇した。食事量は徐々に低下傾向にあったが活気は比較的保たれた。関節腫脹圧痛はない。褥瘡や皮疹はない。【検査結果】CRP 17.81 mg/dL、ESR 120 mm/hr、フェリチン 415 ng/mL、sIL-2R 1630 U/mL、自己抗体検出せず、尿蛋白・潜血陰性、尿pH 9.0、尿K 24.3 mEq/L、尿β2-MG 33100 μg/L、全身CTで腫瘤なし、軸突起周囲に石灰化なし。【経過】赤沈が100 mm/hrを超える発熱の原因は心内膜炎、骨髄炎、薬剤熱、膿瘍、膠原病、悪性腫瘍があるが、身体・検査所見より薬剤熱以外は否定的であった。尿β2-MG著明高値と電解質所見から近位尿細管障害が示唆された。尿細管障害を来しうる常用薬としてバルプロ酸とゾニサミドが挙げられ、薬剤性尿細管障害が発熱を伴った症例の既報を参考に、抗てんかん薬の変更を慎重に行った。ご家族とも相談し、初めにバルプロ酸を漸減、中止し、並行してレベチラセタムを導入し、次いでゾニサミドを中止した。徐々に炎症が低下し食事量も回復した。介入開始後2か月で解熱し、尿β2-MGも半年後に正常化した。【考察】近位尿細管障害はFanconi症候群と呼ばれ、発熱を伴う場合があり、バルプロ酸やゾニサミドが原因の報告がある。これらは10年以上の使用歴があっても生じる。本症も抗てんかん薬の長期使用による蓄積性の尿細管障害が閾値に達し炎症を生じたと考えられた。【結語】抗てんかん薬使用中の発熱では、長期使用歴があっても抗てんかん薬による発熱を鑑別に想起する。