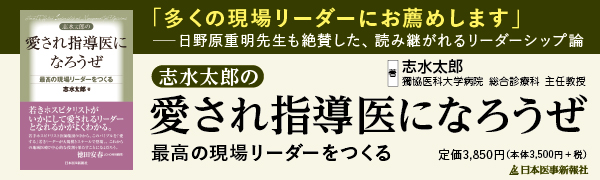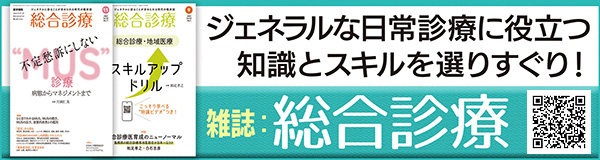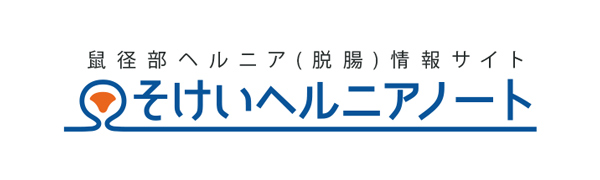[P-075] 食思不振の鑑別に考慮させられた一例
【症例】88歳女性【主訴】食思不振及び肝障害【既存症】76歳高血圧症,86歳:発作性心房細動【嗜好歴】過去に喫煙:10本×50年【現病歴】従来A病院にX年から発作性心房細動で通院されていた.しかし,通院困難となりX+10年(86歳)から,近医(開業医)に通院するようになり内服継続していた.X+13年2月26日より全身倦怠感と食思不振があり,ビタミン剤等の連日点滴加療を受けたが改善なく,3月2日の血液検査で肝障害を認めたため,同月4日に当院消化器内科紹介.食事摂取できず同科に入院.【身体所見】身長 160 cm,体重 33.9 kg,BMI 13.2,血圧 130/85mmHg,脈拍 100/分,不整.SpO2 96%,結膜の黄染や貧血なし,胸腹部特記事項なし,下腿浮腫軽度あり.【検査結果】WBC12800/μL,Plt13.5万/μL,GOT132U/l,GPT 116U/l,γGTP181U/l,T-Bil1.36mg/dl,D-Bil0.57mg/dl,BUN29mg/dl,Cre0.80mg/dl,BNP614pg/ml,心電図:HR140bpm,心房細動,心室性期外収縮,広範囲の陰性T,QTc0.414秒【経過】上記数値より心不全傾向がありフロセミド,食欲不振に関しては補液で加療された.また状態安定すれば上部及び下部内視鏡検査予定であったが改善せず,第5病日に当科コンサルトとなった.カルペリチドで心不全加療を開始するも心房細動継続し同日突然の心肺停止となりCPRで蘇生に成功し,以後ICU管理とした.その後心電図上QT延長があり,Torsade pointesが持続したため,Mgの投与及び低K血症合併に対しKの補充を行うことで徐々に不整脈やバイタルサインは安定した.また,前医からベプリジルが継続されていたため,直ちに中止した.(血中濃度は治療域であった)ベプリジル中止後は,肝機能や心不全は改善傾向となり,第9病日より徐々に食事摂取できるようになった.しかし,洞調律復帰後も左室壁運動低下残存したため,第15病日虚血性心疾患除外目的で心臓カテーテル検査を行い,冠動脈に有意狭窄を認めず,何らかの心筋症の可能性は否定できなかった.ICU退室後は,廃用を強く認めたため心臓リハビリテーション施行し第56病日退院した.【考察】食思不振の原因として,まず消化器疾患を想定するが,特に高齢者では薬剤性の鑑別が不可欠と考えさせられた症例であり文献的考察を加え報告する.