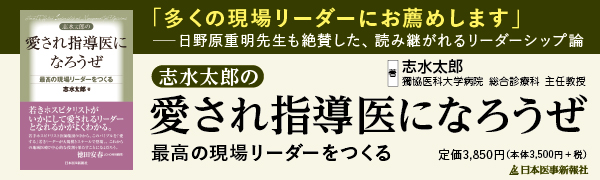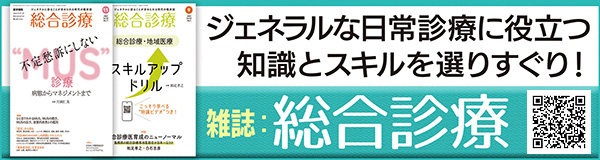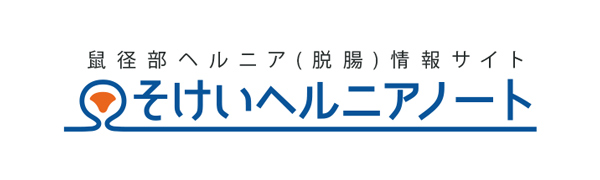[P-113] 飢餓状態に対して栄養療法開始後に肝障害が悪化し肝不全となった高齢女性
【背景】レビー小体型認知症のため施設入所中
【症例】78歳 女性
【主訴】発熱・食思不振
【病歴】腰椎圧迫骨折を契機に寝たきり状態となり、食欲も低下した。入院2か月前からさらに食欲低下し摂食量が減少した。受診前日に発熱が出現し精査目的に入院となった。
【所見】血圧126mmHg/85mmHg、心拍数 83回/分、呼吸数 14回/分、体温 37.7℃、SpO2 99%(RA)、BMI 11.93
眼球結膜黄染なし、腹部平坦軟、圧痛なし。
尿検査では尿中赤血球 30-49個/HPF、白血球5-9個/HPF、細菌尿を認めた。
血液検査ではAST253U/L、ALT503U/L、γGTP160U/L、ALP229U/Lと混合性肝障害を認めた。凝固異常は認めなかった。
【経過】
発熱の原因として尿路感染症の診断で抗菌薬を開始した。るいそうが高度のため末梢からビーフリード輸液を開始した。
入院後5日目にさらに肝酵素上昇、凝固延長を認めたため抗菌薬、ならびに他の薬剤も中止したが、肝機能は改善しなかった。Refeeding症候群の可能性を考え、栄養投与の調整を行ったがさらに肝障害は増悪した。低血糖が頻発するようになり、入院後20日目に死亡した。
【考察】
入院時に認めた肝障害について血液検査や画像検査から肝炎などの一般的な肝障害の原因は否定的であり、薬剤性も疑い内服薬すべてを中止したが、肝障害は改善せず増悪した。
栄養投与開始後に肝障害が増悪したことからRefeeding症候群による肝障害を疑い栄養増量を控えたが、低血糖が頻発した。Refeeding症候群と鑑別すべき肝障害として、飢餓状態による肝障害がある。飢餓状態による肝障害のピークは栄養開始後約 2~5 日後、Refeeding症候群では数週間後とされる。また、低血糖は重症肝不全のマーカーである。本症例では、飢餓状態による肝障害を疑いむしろ栄養増量を続けていくべきであったと考えられる。
【結語】
Refeeding症候群と飢餓状態による肝障害の鑑別に苦慮した肝不全の症例を経験した。