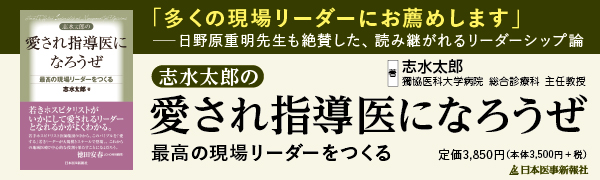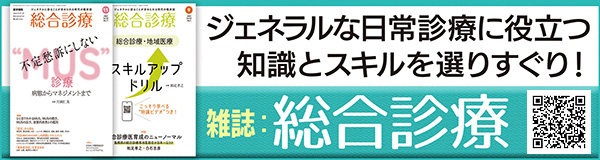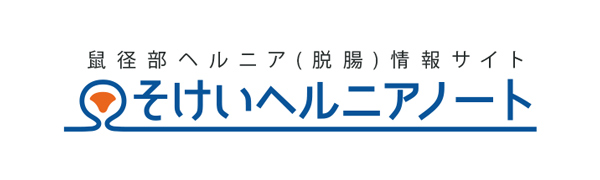[P-102] 頭痛を契機に診断に至った神経型ベーチェット病の1例:リウマチ性疾患における無菌性髄膜炎の鑑別
【背景】総合診療において頭痛は頻度の高い症候である。無菌性髄膜炎は原因疾患の一つであり、多くはウイルス感染症に由来するがリウマチ性疾患も鑑別が必要である。今回我々は、頭痛を主訴とした急性型神経型ベーチェット病を経験したので報告する。【症例】26歳、女性。【主訴】発熱、頭痛。【病歴】生来健康。4日前から持続する発熱と後頭部頭痛を主訴に当院総合診療科を受診した。【現症】身体所見で、口腔内アフタ性潰瘍、両下腿の結節性紅斑、両側膝関節の腫脹と圧痛を認め、神経学的所見では項部硬直およびjolt accentuation陽性であった 。【検査所見】血液検査にて白血球 5500/μL、CRP 2.82 mg/dL、髄液検査では初圧 200 mmH2O、細胞数 299/μL(単核65:多核35)、蛋白 122 mg/dL、糖 53 mg/dLで、各種細菌培養およびウイルスPCR検査は陰性であった。また、頭部MRIで異常信号はなかった。【経過】入院当初、無菌性髄膜炎に対するempiric therapyとしてアシクロビルの投与としたが、口腔内アフタ性潰瘍の再発性を確認し、ベーチェット病診断基準(厚労省)の主症状2項目、副症状2項目を満たす急性型神経型ベーチェット病(不全型)と診断した。パルス療法を含むステロイド治療により発熱、頭痛、皮膚粘膜症状はすみやかに改善し、コルヒチン併用下でステロイドを漸減、中止した。その後、コルヒチン単剤で再燃なく経過している。【考察】本例では髄液中に多核球と単核球が混在し、皮膚粘膜症状が随伴したことより神経型ベーチェット病と診断した。ベーチェット病における神経病変の出現は厚労省または国際診断基準の充足時より平均4-5年後とされ、神経症状を初発としベーチェット病の診断に至ることは稀である。無菌性髄膜炎ではベーチェット病を含めたリウマチ性疾患の鑑別も必要で、その診断には神経外症状も含めた詳細な病歴聴取、身体診察による随伴症状・徴候の把握が重要である。【結語】皮膚粘膜症状が随伴する無菌性髄膜炎ではウイルス感染症に加え、神経型ベーチェット病などのリウマチ性疾患も想起することが望まれる。