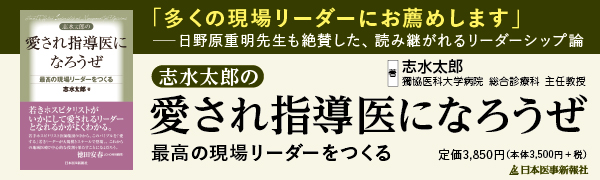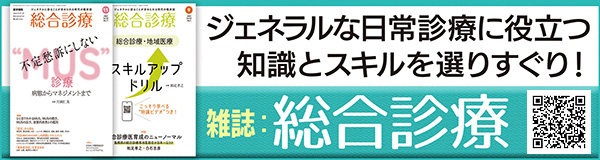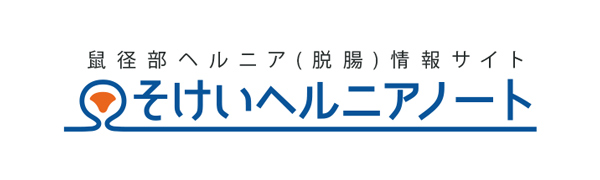[P-103] Granulicatella elegansによる感染性心内膜炎によって急速進行性糸球体腎炎を呈した一例
【背景】感染性心内膜炎(IE)は糸球体腎炎、Osler結節、Roth斑、リウマチ因子(RF)などのなどの免疫学的現象を呈することが知られているが、Granuilicatella属によるIEは慢性経過で発症することが知られており、急速進行性糸球体腎炎(RPGN)を合併した報告はない。【症例】63歳男性【主訴】倦怠感【病歴】生来健康で病院通院歴はない。数ヶ月前から腰部痛を認めていた。その後、倦怠感の出現を認めるようになり徐々に増悪を認め救急受診した。【所見】心音は整で胸骨右縁第2肋間にLevine Ⅲ度の収縮期雑音を認める。Cre 3.47 mg/dLで尿蛋白3+、尿潜血3+と新規の腎機能障害を認めていた(3ヶ月前はCre 0.77 mg/dLで尿所見に異常はなかった)。CRP 7.12 mg/dLと炎症反応の上昇を認めていた。免疫学的検査ではRFは22.4 U/mLと陽性で、クリオグロブリン定量は陽性を示し、低補体血症(CH50 <5 U/mL、C4 7.2 mg/dL、C3 44 mg/dL)を認めた。腹部超音波検査では両側腎種大を認めた。【経過】RPGNを疑い精査目的に入院となった。血液培養よりGranulicatella elegansが検出され、経胸壁心臓超音波検査では疣贅を認めており(僧帽弁に18mm、大動脈弁に8mm)、IEの診断となった。頭部MRIでは多発脳梗塞を認め、腰部MRIではL4/L5に化膿性脊椎炎を認めた。抗生剤加療を行い、手術にて軽快し退院した。その後、血清Cre値、クリオグロブリン血症、低補体血症は改善した。【考察】IEの診断基準として広く流用されている改定Dukes基準の小基準の中にも免疫学的現象の記載がある。本症例においてもRF陽性で臨床的にRPGN呈しており、免疫学的現象を認めた。Granuilicatella属は栄養要求性連鎖球菌(NVS)に分類され発育に時間を要する特徴があり、質量分析法の進歩により検出されるようになってはいるが、IEの報告は全体の5%と少ない。また重症化や予後不良が多いとも言われており、今回は多発性脳塞栓、化膿性脊椎炎も合併し、二弁置換を施行するに至ったケースであった。【結語】RPGNの鑑別には、特異的な抗菌薬治療が存在し外科的な治療が適応となる可能性があるIEを鑑別に挙げるべきであり、丁寧な身体診察による心音聴取は欠かせない。