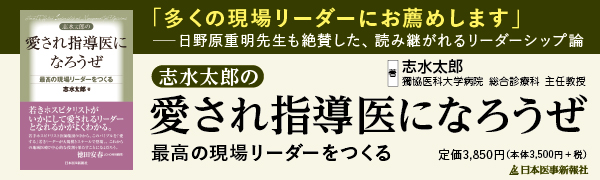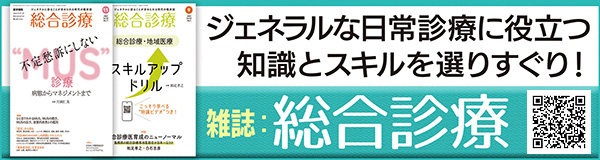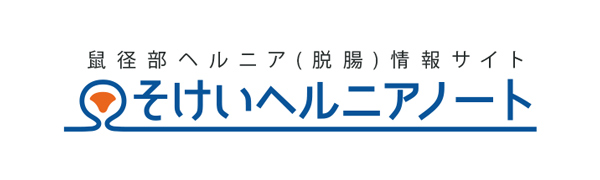[P-118] 東洋医学的なアプローチが奏功した9歳女性の起立調節障害の一例
【背景】起立調節障害は小学生では約5%に発症し,その半数が長期欠席となり,一年後の回復率は約50%,2〜3年後の回復率も70〜80%と,生命予後は良好だが有症状時および症状回復後もADLに多大な影響を与えうる疾患である.治療には難渋することも多く,医療者自身も診療を負担に感じる場合がある.【症例】9歳女性
【主訴】登校企図時の腹痛
【病歴】X年6月頃から、朝登校しようとすると腹痛が3回/週ほどの頻度で出現し学校を休むことが出てきた.夏休みに入り,ツムラ小建中湯エキス顆粒 3g 分1にて内服開始し,日中は母の職場で過ごすようになった.この間,NRS 9/10程度で腹痛は持続していた.二学期が始まり毎朝腹痛のため登校できないことが続くようになり,小児科受診し採血および起立調節障害のスコアリングの結果,起立調節障害疑いとして生活指導にて経過観察となった.その後も登校できないことが続いているため10月15日受診となった.
【所見】四診において舌尖紅刺,白膩厚苔,肝脾に関与する経穴の左右差が目立ち,下腿浮腫(fast pitting edema)を認めた.
【経過】肝脾同病と東洋医学的に診断し,ツムラ柴苓湯エキス顆粒 3g 分2にて内服開始し,1週間後に腹痛はNRS 6/10に改善し,下腿浮腫も改善を認めた.『傷寒論』巻三に「先ず小建中湯之を与え.差へざる者は,小柴胡湯之を主る」とあり,柴苓湯中の小柴胡湯の方意が奏功したと考え,東洋医学的な治療が有効と判断し鍼灸院にも紹介した.10月22日初診,11月4日に4診目の施術の後,1時間程度から一日毎に出席時間が増え,登校可能となった.
【考察】水分や塩分摂取励行といった西洋医学的な介入では改善が乏しかったが,漢方治療に好反応があり,鍼灸を併用したところ,速やかに治療効果が得られた.紹介先の鍼灸院では少数鍼,接触鍼を用いた低侵襲治療を行なっており,その有効性と即効性が有利に働いた症例と考えられる.
【結語】機能性障害に対し,漢方や鍼灸を用いた治療の有効性が確認されたとともに,信頼できる鍼灸院との連携が重要と考えられる.