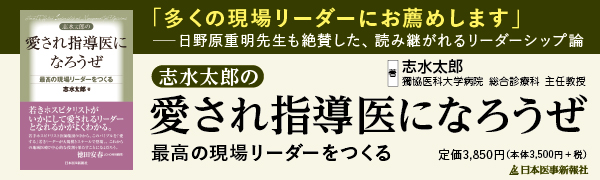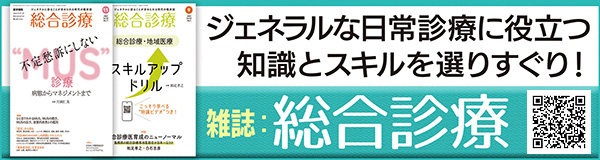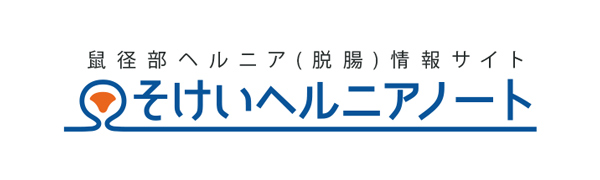[P-121] ものわすれ外来(認知症専門外来)における回想法アプローチ
【背景・目的】ものわすれ外来(認知症専門外来)で行っている回想法アプローチは、患者さんや御家族とのコミュニケーションを向上させる有力な手法であり、一般診療においても運用が十分に可能なツールと考える。今回の発表で回想法の中で比較的容易に実践が可能なTIPSを具体的に紹介することで、診療医の日常診療でのコミュニケーション向上の一助としたい。【方法・結果・考察】演者は、2021年6月から、大分県東南部に位置する佐伯市(人口7万人、高齢化率41%)の二次救急病院(244床)に内科部長として赴任して、新たに「ものわすれ外来(認知症専門外来)」を開設した。前任の大分県豊後大野市(人口3万6千人、高齢化率44%)の一次救急病院で8年間に亘って認知症診療を行う中で、地域の高齢者といち早くコミュニケーションを取る手段として、現地特有の医療方言を学ぶ(例:ユーロ=下腿内側、ホメク=熱感がある)ことに加えて、明治時代から昭和前期にかけて発行された郷土絵葉書をデジタル化して、パソコン画面で患者さんや御家族に供覧しながら話を聞くことで患者さんとのコミュニケーションが容易に高まることを実感した。特に、戦前期の1939年以前に出生して、1945年以前に小学校に入学した世代にとって、「通っておられた小学校に奉安殿はありましたか?」という質問は、心理療法の短期療法における「ミラクルクエスチョン」のように、筆者が接した9割以上の認知症患者がその施設と当時の懐かしい心象風景を笑顔と共に回想して医療者に語って下さるきっかけとなっている。演者は郷土史愛好家であり、祖父母から受け継ぎ、医学生時代から県内の古書店を廻って収集した1000枚以上の郷土絵葉書をもとに、新任の佐伯でも回想法アプローチを行ったが豊後大野市と同様の反響があり、地元紙やメディアで活動が大きく取り上げられた。【結語】回想法は欧米で広く知られているものの、日本の医療機関であまり知られていない印象がある。今回の発表が日常診療でのコミュニケーション向上の一助となれば幸いである。