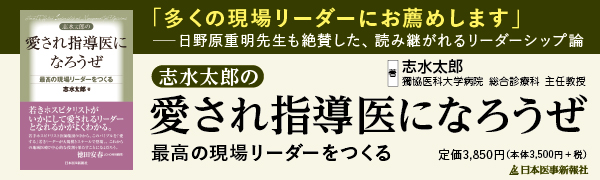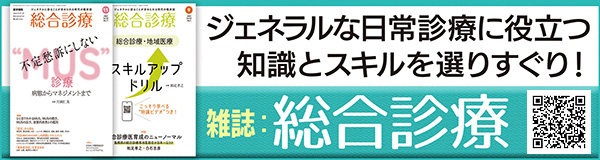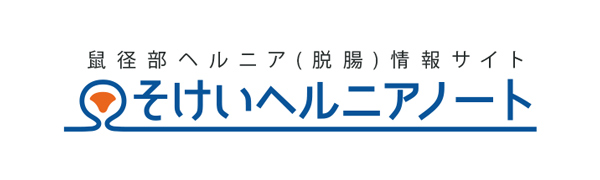[P-124] 抗菌薬単独で治療した巨大肝膿瘍の一例
【背景】Streptococcus intermediusは口腔内や消化管の常在菌で、化膿性肝膿瘍をきたす細菌として知られる。化膿性肝膿瘍は死亡例もあり、適切な診断と治療が必要である。特に径5cmを超える肝膿瘍は抗菌薬単独では重症化する可能性があり、外科的ドレナージを行うことが一般的である。今回、径10cm以上の巨大な化膿性肝膿瘍に対しドレナージせず抗菌薬単独で治療した症例を経験したので報告する。
【症例】66歳男性
【主訴】発熱
【病歴】来院3日前から39℃の発熱を認め、悪寒を伴うため救急外来を受診した。
【所見】来院時バイタルサインは、体温39.7℃、脈拍128bpm、血圧106/62mmHg、呼吸数16回/分、SpO2 95%(室内気)。意識は清明。身体診察では異常を指摘できず。血液検査では白血球14,500/µL(好中球87.7%)、CRP>32mg/dL(上限以上)、プロカルシトニン>10.0ng/mL(上限以上)。CTでは肝S4~S6に境界明瞭な最大径10 cm以上の多発する低吸収域を認めた。
【経過】肝膿瘍または肝腫瘍の疑いと診断し、抗菌薬MEPM 3 g/日で投与を開始。第8病日に血液培養でStreptococcus intermediusが検出され、CT結果と併せて化膿性肝膿瘍と診断した。穿刺ドレナージを検討したが患者の同意が得られず、抗菌薬をCTRX 2 g/日+MNZ 1500 mg/日投与に変更して継続した。第13病日には解熱し、第40病日にはCRPも正常範囲まで低下し、CTでも肝膿瘍はほぼ消失した。抗菌薬治療を終了した。第42病日に退院、その後3カ月のフォローアップで再発無く経過した。
【考察】肝膿瘍では超音波またはCTガイド下でのドレナージが治療法となるが、本症例では糖尿病やアルコール依存症、悪性腫瘍などの免疫不全のリスク因子がなく、抗菌薬単独でも重症化せず治療が奏功したと考えられた。上部・下部内視鏡検査では細菌の侵入門戸を特定できなかったが、可能性としては歯周病が考えられた。
【結語】化膿性肝膿瘍の患者でリスクが低い場合でドレナージができない場合、抗菌薬単独治療も可能ではある。