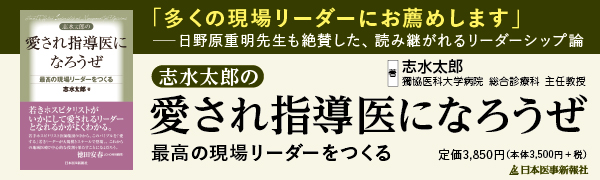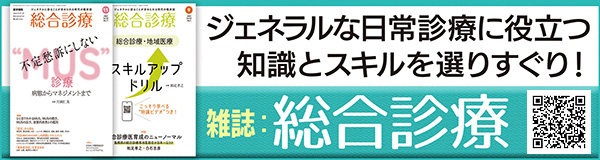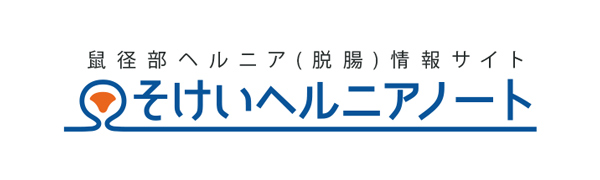[P-130] ウイルス性髄膜炎疑いに対し加療中に両側顔面神経麻痺を来した症例
【背景】髄液中の細胞数増加は感染症,悪性腫瘍などを誘因として生じる.髄液中の細胞数増加を伴う頭痛・嘔気のある髄膜炎の加療中に両側の顔面神経麻痺を呈した症例を経験したため報告する.【症例】54歳,男性 【主訴】発熱,嘔吐 【既往歴】副鼻腔炎 【現病歴】入院の9日前から38.4℃の発熱,7日前から頭痛が出現し,近医で副鼻腔炎としてセフジトレンピボキシルの内服をしていた.しかし症状は改善せず,当院救急科の外来を受診したが,頭部CTで異常なく,嘔気に対する対症療法のみで帰宅した.しかしその後も症状が継続したため,総合診療科の外来へ紹介受診となった.髄液検査でリンパ球が優位の細胞数の上昇を認め,ウイルス性髄膜炎の疑いで入院となった. 【所見】髄液検査でリンパ球優位の細胞数の上昇(30個/μL) 【経過】抗菌薬・抗ウイルス薬を投与するも症状は残存し,後日に髄液の再検査を行うと細胞数は49個/μLとさらに上昇を認めた.第6病日,下唇のしびれを訴え,それを発端に徐々に顔面神経麻痺,舌下神経麻痺が進行し,第10病日には両側で表情筋の随意運動をほぼできなくなった.頭部MRIでは特記すべき所見は認めなかった. 筋電図検査で顔面神経核の異常が示唆され,第12病日より大量ガンマグロブリン投与を行ったところ,柳原法で4点であった顔面神経麻痺は14点に改善を認めた.さらに第18病日から3日間のステロイドパルス療法を行った後,リハビリテーションを導入し退院となった. 【考察】両側性の顔面神経麻痺は稀で,その原因は多岐にわたる.顔面神経麻痺に対し腰椎穿刺を施行した症例の中には,癌性髄膜炎や,ステロイドパルス後にリステリア髄膜炎を引き起こした症例など,致死的な疾患も散見された.今回のように下唇の僅かな麻痺から両側性へ伸展することもあり,早い治療介入のためにもよく患者の訴えを傾聴する必要がある.【結語】髄膜炎の患者では神経症状の発現に注意すべきである.