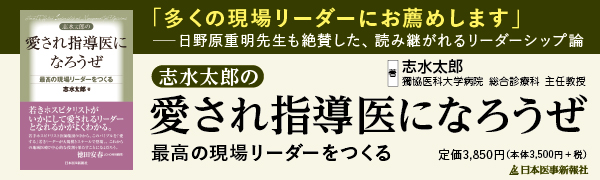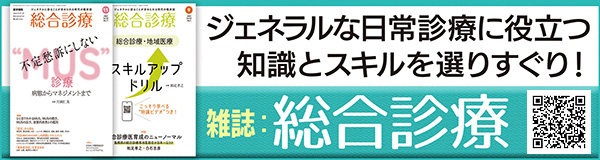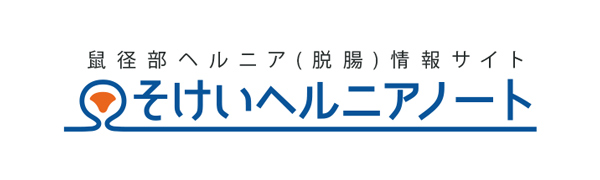日本プライマリ・ケア連合学会における学術研究活動の歩みと課題
2010年に発足した日本プライマリ・ケア連合学会は、プライマリ・ケア医療提供者全体に研究リテラシーを普及することにより、プライマリ・ケア研究の質の向上、ひいてはプライマリ・ケア医療の質の向上に貢献することを目的と掲げて学術研究活動をスタートした。
大きく3つの活動を柱としているが、最初は学会発表の場の提供である。一般口演、ポスター発表の場を提供し、コロナ後はWebでのオンラインポスターを導入。更に、学会発表において優秀な演題に与えられる日野原賞制度、国際活動としてのInternational session、医学生の発表の場としての学生セッションなどを設置し、研究発表の場を拡大すると同時に質の向上を図ってきた。
二番目は研究推進と人材育成である。当初から実施してきた研究助成は個人助成とチーム助成を行い、学術集会での報告と英語論文化を前提としている。更に、2017年度からは未来研究リーダー育成プロジェクトを開始し、研究リーダーの育成をスタート。毎年1〜2名を選抜して3年間の講義、オンライン指導を通じて研究計画から実施、論文化まで取り組んでもらっている。
三番目は論文発表の場の整備である。2017年には学会英文誌の発行数を年2回から年6回へと増やし、オンラインジャーナル化と同時にOpen Accessを実現。2019年にはPubMed Centralに収載となり、現在はImpact factorの付与を目指して、アジアを代表するプライマリ・ケア領域ジャーナルを目指している。
最後に、2019年より日本臨床疫学会、米国内科学会日本支部と共催するPCR-Connectにもふれる。これは筆者が米国にてNAPCRGに参加して、若手からベテランまで幅広いプライマリ・ケア研究者が一同に会し、研究発表はもちろん、様々な研究学習WS、Interest group、研究計画の発表と質疑などを展開している様子に衝撃を受け、その日本版を目指してスタートした企画である。まだ参加者は200名程度と少ないが、日本の研究リーダーを涵養する場として今後大切に発展させていきたい。
当日はこうした実践に基づいて見えてきた学術研究活動の課題を論じていきたい。